Interview / I I I I
デザインアーカイブの歴史と事例を知る
新たな国家資源としてのデザイン
──ネットワーク型デザインアーカイブの構築へ

日本のデザインアーカイブを起点にした経済発展や国家としての誇り、クリエイティブコンフィデンスの醸成を目指した事業が2024年に始動しました。「日本のデザイン資源の最大限の活用が必ず新たな産業を生み出す」。その想いのもと、国内各地に存在するデザイン資源をつなぐ活動はどのように進められてきたのか。パノラマティクス主宰として先駆的なデザインワークと行政との協業に豊富な経験を持つ齋藤精一氏と、デザインをテーマにした番組制作のプロデュースにも従事し一般社団法人Design-DESIGN MUSEUMの代表理事を務める倉森京子氏が、これまでの議論を振り返りました。
日本のデザイン資源をつなぐ試み
──「我が国企業のデザイン資源を活用した海外展開促進事業」において、2024年度には計3回の有識者会議をとおしてデザインアーカイブのあり方が議論されてきました。有識者会議から浮かび上がってきたのは、日本には多くの団体による優れたアーカイブが存在する一方で、それらアーカイブの維持や拡充が各団体に委ねられていること、継続性の担保が難しいことといった現状です。これまでにさまざまな会議体に参加されてきた齋藤さんと倉森さんには、それらの議論を俯瞰する視座があると思います。
齋藤精一(以下、齋藤):2012年に三宅一生さんと青柳正規さんが「国立デザイン美術館をつくる会」を立ち上げて以降、国を挙げたデザインアーカイブやデザインミュージアムの必要性を問う議論は多く実施されてきました。インフラとしてのインターネットが整備され、また個々の団体による物理的な所蔵の限界が見えてきたことから、「ネットワーク型」という性格のアーカイブを模索する動きが年々強まってきているように思います。
倉森京子(以下、倉森):2015年に開始された「文化庁アーカイブ中核拠点形成モデル事業」は、ネットワーク型アーカイブとして先駆的な取り組みとなりました。グラフィック、プロダクト、ファッションの3分野を対象に、京都工芸繊維大学美術工芸資料館、武蔵野美術大学美術館・図書館、文化学園大学が連携し、各拠点とそれぞれの所蔵データをつなぐ試みがなされました。
──アーカイブの対象として、どこまでをデザインの範疇とするかという定義を問う議論も続いていると伺っています。
倉森:私たちが2019年に設立した一般社団法人Design-DESIGN MUSEUMの活動を重ねるなかで、「人がつくったものすべてがデザインである」という考えを持つようになりました。そこから、全国各地にある県立美術館や郷土資料館、企業資料館、個人コレクションも含めて連携した総体をもって、「日本中がデザインミュージアムになるといい」という構想を抱いています。全国のネットワークを背景としながら、例えば国立新美術館の一室が国立デザインミュージアムの常設展示室になるといったようなところから、リアルな場を構えることができないかというアイデアを練っています。
齋藤:そのようにデザインを幅広く捉えたとき、日本に現存するデザインアーカイブの総量は、イタリアにも中国にも負けない規模を誇ります。ただ、そのアーカイブを総括的に推進する主体はどこにあるべきかという議論を乗り越えられない時期がしばらく続いていました。
「DESIGN デザイン design JAPAN Design Resource Database(以下、DESIGN デザイン design)」は経済産業省が所管する事業です。デザインを国の資源として明確に位置付けたことは大きく、これまでの議論を前に進めることにつながりました。過去のデザインを生きたものとして扱い、新たな産業や未来へとつなげていく。アーカイブが持つ価値や意義のシフトチェンジが起きています。
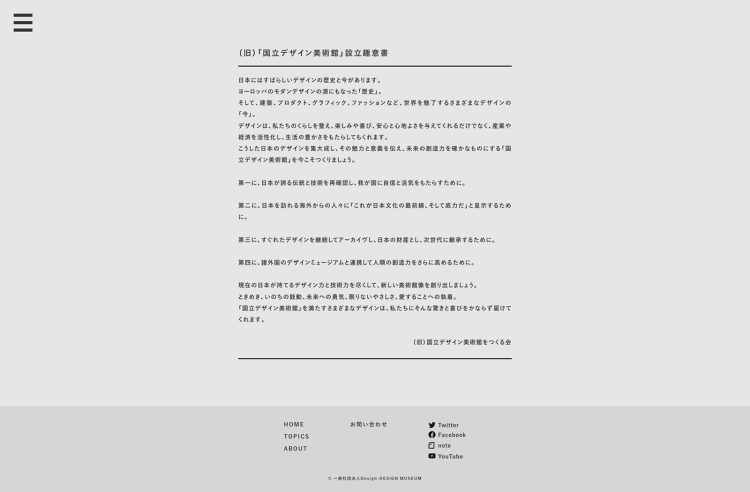
データベースの構築と展望
──2024年度の活動のひとつとして、全国のデザイン資源を所蔵する15施設とのネットワーク化が実施されました。各団体が所有するアーカイブデータとの連携はどのように進められたのでしょうか。
倉森:まず具体的な作業として「DESIGN デザイン design」のデータベースに登録するデザインそれぞれに対して、制作年や発売年、寸法や著作権登録番号、所蔵先といったさまざまな情報を入力していただいています。既存のデータベースに付随する作業との重複、二度手間といったことが生じてしまうなかで、今後どうしたら多くの施設に入力いただきやすくできるかを、有識者会議のメンバーである国立アートリサーチセンターの川口雅子さんにも協力いただいて、上手な統合方法を模索したいと考えています。
齋藤:エクセルやウェブサイトなど各団体がもつ小さなデータベースを使った、「車輪の再発明」とも言えるプロセスです。日本デザイン団体協議会(DOO)のように、これまで分散していたデザイン団体が合流する取り組みがありつつも、企業や大学、デザイン事務所すべてをつないで共有知をつくることには誰も着手することができませんでした。国という主体であれば、そういった各地の団体やアーカイブをひとつなぎにすることができるはずです。
──国という主体のなかにも、省庁をはじめとする組織間のギャップがありそうです。
齋藤:「DESIGN デザイン design」の展望にもつながる話ですが、豊富なデザインアーカイブをつくった先にある「横展開」についてもアイデアを広げているところです。内閣府や国立国会図書館が展開する「Japan Search」におけるデザイン分野との連携、国土交通省と連携した建築分野への応用、文部科学省と連携したデザイン教育への活用など。
そのような取り組みが積み重なっていけば、国としてひとつのアーカイブを構築するという発想や、アートやデザイン、映画や音楽といった分野を横断したアーカイブを現代的なかたちでつくっていける可能性が生まれてくるのではないでしょうか。
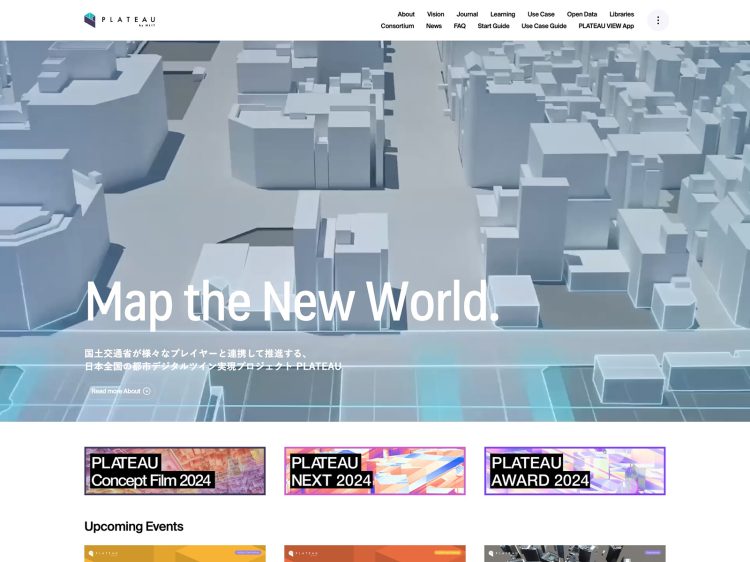
デザイン資源の活用に向けて
──デザイン領域のアーキビストや学芸員は、アート領域に比べて圧倒的に少ないという現実があります。「DESIGN デザイン design」が始動したことによって、人材の拡充とともに、デザイン領域ならではのアーカイブフォーマットの構築も、より求められていくのではないでしょうか。
倉森:デザインには、日常生活のなかで実用性や機能性が求められる道具も含まれています。作品として記録、収蔵するだけでなく、実際に使って役に立つものとしてデジタルデータを公開していくことは、アートとの違いという意味でも、本来的なデザインのあるべき姿ではないでしょうか。
齋藤:倉俣史朗さんの「ミス・ブランチ」の扱い方として、それがポディウムに載っていればアート作品として見なされ、部屋やテラスで子どもたちが座れるようなかたちであればデザインとして見なされるという現象が起きると思うのです。アーカイブのあり方としても、デザインとアートは分けて考えるべきで、デザインにおいては活用という側面を強めていかねばいけないのだと思います。
──デザイン資源の活用とは、具体的にどのようなかたちで実践されていくのでしょうか。
齋藤:博物館や大学、企業やデザイン事務所など、分散するさまざまなデザインアーカイブとの連携を進めていくなかで、団体によってデザインアーカイブという事業や知的財産に対する考え方、ステータスがまったく異なる状況を目の当たりにしています。東芝未来科学館の運営見直しが発表されたのも、この活動を始めた頃でした。ネットワークの構築に賛同いただきつつも、個々のデザインアーカイブが置かれている状況が違いすぎることから、共通解としての活用のかたちを探りきれていないというのが現状です。
国内施設との連携や、約40件のデザイン資源のデータベース化、「DESIGN デザイン design」のローンチなど、ネットワーク型デザインアーカイブの入り口にようやく立つことができました。2024年度時点の「DESIGN デザイン design」のウェブサイトは、データベースであると同時に、研究と考察の場として公開されるものです。次年度以降は、デザイン資源の価値創造についてあらゆる角度から試行錯誤していきます。
倉森:ネットワークへの参画団体やプロフェッショナルな個人にとっての活用を模索するだけでなく、デザインに少しだけ興味があるといったような訪問者への価値提供も考えていかなければなりません。これまではアーカイブの構築そのものが目的になってしまう取り組みもあったように思います。
データベースとしての精緻なつくりこみはもちろん大切な作業です。それと同時に、アーカイブをひとつのサービスやコンテンツとして捉え、どんな人に、どのように楽しんで使ってもらいたいのかといった観点をもつことで、デザインに関心のある人もそうでない人も巻き込んでいく。「自分の身の回りに、実はこんなにも豊かなデザインが広がっていた」といったピュアな気付きを持ってもらえるようなアプローチも必要に思います。
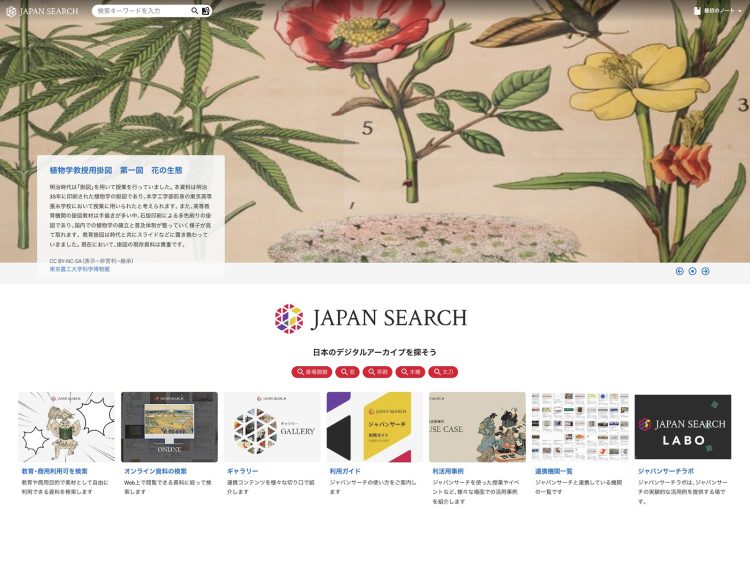
ユニバーサルなデザインアーカイブへ
──日本のデザインを海外にアピールすることで産業振興につなげたいという意図が本事業には込められているように思います。
倉森:日本のデザインが3Dスキャンデータとして世界中のクリエイターの手に渡り、ビデオゲームやバーチャルコンテンツのなかで活用されるといった展望は、事業の当初から掲げていることです。「このアーカイブには日本のデザインのすべてがある」と期待感を持ってアクセスしてもらうために、個人コレクターまで連携の輪を広げていくことも視野に入れています。
──若い世代が過去のデザインを見たときに新鮮な気持ちで面白がるという現象にも期待ができます。
齋藤:世代交代は確実に進んでいます。新しい世代によるデザイン団体も生まれてきているなかで、組織や年代の壁を越えたユニバーサルなアーカイブづくりを進めていかなければいけません。名作と称えられるデザインだけでなく、活躍する現役世代のデザインも収蔵されていくような、生きたアーカイブのあり方についても議論が進められています。
「DESIGN デザイン design」の活動が継続していくためには、このデザインアーカイブに寄与することがなんらかの経済効果につながっているということを協力者の方々が体感できる必要があります。人が集まる、売り上げが伸びるといった価値の示し方を考えながら、自走するデザインアーカイブを構築していきたいです。
※2025年2月時点のインタビューです。
プロフィール
倉森京子 (くらもり・きょうこ)
株式会社NHKエデュケーショナルコンテンツ制作開発センター 美術教養グループ
チーフ・プロデューサー。
1987年NHK入局。ディレクターとして岡山放送局に赴任。その後、社会情報番組部を経て、1996年からはNHKおよびNHKエデュケーショナルで「日曜美術館」を中心に美術番組を担当。美術やデザインに関する番組や、番組から展開するイベントを開発する。
制作した主な番組に、NHKスペシャル「桂離宮」。4K番組「三宅一生 デザインのココチ」「ビューティフル・スローライフ」。8K番組「ルーブル美術館」「オルセー美術館」「国宝へようこそ」。シリーズ番組として「テクネ 映像の教室」「びじゅチューン!」「やまと尼寺 精進日記」「TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇」など。2020年より、番組と展覧会を両輪として進めるプロジェクト「デザインミュージアムジャパン」に携わる。
一般社団法人Design-DESIGN MUSEUM代表理事。女子美術大学特別招聘教授。国立新美術館評議員。
齋藤精一(さいとう・せいいち)
株式会社アブストラクトエンジン、パノラマティクス主宰。
1975年 神奈川県伊勢原市生まれ。建築デザインをコロンビア大学建築学科(MSAAD)で学ぶ。2006年に株式会社ライゾマティクス(現:株式会社アブストラクトエンジン)を設立。社内アーキテクチャ部門を率いた後、2020年に「CREATIVE ACTION」をテーマに、行政や企業、個人を繋ぎ、地域デザイン、観光、DXなど分野横断的に携わりながら課題解決に向けて企画から実装まで手がける「パノラマティクス」を結成。
2023年よりグッドデザイン賞審査委員長。2023年D&AD賞デジタルデザイン部門審査部門長。
2025年大阪・関西万博EXPO共創プログラムディレクター。




